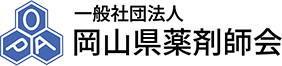味の世界史を人類の起源から見ると、人類はもともとアフリカに居住していたが、今から7~8万年ほど前にアフリカを出て、世界各地に住みつくようになった。こうして世界各地に散らばった人類は、それぞれ気候区の異なる地域に住むことになった。そして人類は、やがて自分たちの土地で取れた作物を、別の地域で取れた作物と交換するようになった。そしてそれを加速化したのが大航海時代です。
大航海時代は、経済力がより強かったアジアにヨーロッパが挑戦し、やがて、ヨーロッパが世界支配する時代が始まります。そのため、アジアの香辛料を求めるヨーロッパの人々の航路は、時に残虐な戦争と成すこともありました。
本国からはるか離れた国から輸送するシステムが形成され、帆船から蒸気船へと輸送手段が転換することで、世界各地の間の実質的な距離は一気に縮まり、食品の輸送量は一挙に増えました。
ここで注目すべきは、香辛料の商人は、薬商人でもあった。彼らは単に香辛料商人や薬剤師にとどまらず、社会的にも信用されていて、公的な要職に就く者も多かった。取扱商品は香辛料以外にも医薬品、リキュール、紙、インク、果物、ナッツがあった。香辛料は薬や疾病予防として特に効果的であると考えられており、また、宗教的な儀式として「香」として、香水や化粧品に蒸留されたりした。裕福な消費者によって貴重な消費材として珍重された。
肉、魚、スープ、甘い料理、ワインの風味付けに至るまで、中世の美食には、香辛料の盛り合わせを楽しんでいた。
中世のヨーロッパ経済は、アジアの経済より低い水準にあり、ヨーロッパ人は、料理を美味しくするうえに薬効もある香辛料を求めており、いよいよ自ら海外に進出することを試みる様になった。
ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリスは、東南アジアで生長する香辛料を求めて、長距離の航海をしました。ヨーロッパの船がヨーロッパの海を出発して、アフリカ大陸南端を通ってアジアに至り、そして同じヨーロッパの船で、アジアからヨーロッパへと香辛料が輸送されることになりました。世界各地へと出かけることにより、ヨーロッパ人の世界の地理に関する知識が、だんだんと正確になりました。やがて、ヨーロッパ人の好みは、砂糖へと移り変わっていきました。
砂糖は世界史を大きく変えていきました。砂糖は中世期後期には、医療や料理で多用される重要な食品になりました。近世には、砂糖は贅沢品から必需品に変わっていきました。人々の味覚の変化です。そして、紅茶、コーヒー、チョコレート等を甘くするものに欠かせなくなりました。
砂糖の原料のサトウキビは、東南アジアのニューギニアで栽培され始め、そして、はるか遠くに移植され、ブラジルをはじめとする新世界で栽培されるようになりました。ブラジルの砂糖は主要な生産地となり、ブラジルを支配していたポルトガルの地位は上昇し、ポルトガルの首都であるリスボンは急激に発展しました。砂糖はヨーロッパ人の生活水準を上昇させ、ヨーロッパ人が世界を自由に動かせる存在になりました。砂糖産業は資本主義経済と密接な関係を持つようになりました。ヨーロッパの国々の海外進出により、世界各地のさまざまな食品、作物が世界中で流通するようになり、料理の味覚や食文化も大きく変化するようになりました。しかし、香辛料も砂糖も、どちらも自然の恵みの産物なので、生産量には限りがあります。
それに対して、人工的に化学合成されたうま味調味料の生産量の限界は高いところにあった。外食産業が発達し、多様な食べ物がたくさんにあるのは、うま味調味料や食品添加物があるからです。いわば現代の香辛料です。
長い歴史を通じて、今、我々は世界の味をどこでも、同じように、味わえるようになった。
幸せな時代になったものです。