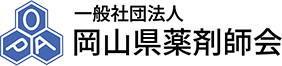現在の日本列島の土台は、ユーラシア大陸の東の果てで、数億年の時間をかけ、様々な地球科学的なプロセスを経て作られた。そして約2500万年前、大陸から独立し始めて、約1000万年前に、ほぼ現在の位置に収まった。
日本列島に現生の人類の生活が顕著に認められるようになったのは、3万8000年前だと言われている。
それから、列島で生活していくためには、資源、すなわち、すぐその日から必要となる水、塩、燃料に始まり、鉄や黄金の「贅沢品」まで、いわば日本列島の「飯のタネ」である。
成り立ち 日本列島、特に東北日本がユーラシア大陸から離れ、現在の位置に到達してからは、大陸から切り離され、現在の位置で水没しかけていた東北日本、海底火山の凸凹の火山列島が見られ、海沿いにはそのような奇岩平野が発達した。大陸的な岩石が織りなす景観の中で、そこで生きる人々は、文化を育んで生活をした。
火山の列島 海溝の沈み込みにより、地下へと運ばれたプレートから解き放たれた水は、嵩を増し、マグマ溜りを作る。そこに周辺から高温の熱源が入り込み温泉を作ってゆく。日本列島は空から雨が降り、地下から豊富な水が供給される「水の恵みの列島」である。「水攻めが運命づけられた列島」でもあった。
大陸の東、大洋の西――湿った日本列島は、大量の水蒸気を含んだ小笠原高気圧になった。とっぷりと覆われた盛夏は、風通しの良い家屋で何とかしのぎ、冬は、外とはさほど温度が変わらない室内で、身を屈めてやり過ごす戦術をとった。夏・冬は言うに及ばず、一年を通じて、花見、梅雨、長雨、台風ありと、季節の変化移り変わりが激しい。それもこれも、日本列島が中緯度に位置し,巨大な大陸の東、巨大な大洋の西に位地していることに起因する。この移ろいやすい天候は、たくさんの詩歌を生む背景となり、緑あふれる大地が維持される素地となった。
塩の道――日本列島には岩塩は分布していない。しかし、海岸線はどこからもそれほど遠くはない所に続いている。我々はこの大陸の東の湿った列島で、塩作りを運命づけられた。太陽の力を最大限に利用して、たくさんの工夫を試みた。現在の製塩業は、天日でなく電力で作られている。
森林、石炭、石油――列島の燃料 日本列島は植生豊かで、肥沃な土壌が存在するが、それは単一の要因ではなく、豊富な降水量、火山の存在、黄砂の供給、岩石の若さなど無数の偶然に支えられている。日本列島がユーラシア大陸から独立する直前、湿った大陸辺縁で作られた石炭は、日本列島にも相続され、日本の高度成長を支えた。また、列島の大改造の時代に細長い海を埋め立てるために一役買った藻は、大量の有機物を地層中へと埋没させ、様々な運動のもと、石油へと姿を変え、我々が回収可能な油層となった。
列島の鉄――列島をくまなく探しても縞状列島の鉄鉱層は出てこない。現在、鉄鉱石を100%輸入している背景でもある。むしろ、伝統的に鉄含有量の低い花崗岩起源のマサ土から鉄を採り、それを使った。列島の変動帯は火山噴火、断層運動、地滑りなどで、岩石は露出し、風化によって新たにミネラルが供給され、豊かな森を維持させるため、地球科学的な変動が絶えず行われた。
列島の錬金術――奈良時代の一大公共事業である大仏建立の最中、日本列島に「金」が存在することが確かめられた。
すぐ手に入る砂金を手始めに、硬い岩石に含まれる金鉱脈へと触手を伸ばした。そして、さらに地下数百メートルまで掘り進み、黄金を求め続けた。
これは日本列島が大陸時代、1億年前に形成された金鉱床から、大陸から自立するイベントとの関連で生まれた金のマグマ溜りの周辺で作られた金鉱床へと採鉱の対象を広げていった道のりであった。日本列島の金鉱床として、北上山地の金鉱床(谷山金山、大谷金山)、佐渡の金鉱床(佐渡相川金山)、南九州の金鉱床(菱刈金山)がある。
暮らしの場としての日本列島 この列島は地球科学的に新しく、かつ極めて活発な変動帯に区分され、気象学的には大陸の東に格付けするモンスーンかつ台風来襲だ。しかし、これらは、風光明媚な景観、肥沃な土地、豊富で美しい水、よりどりみどりの温泉などがある。
日本列島は、「慈悲深い列島」である一方「危険な列島」でもある。一言で言えば「すごい列島」である。凄い列島でどう暮らしていくべきか。
我々が一人一人考えて行きたい、重くて深い宿題である。