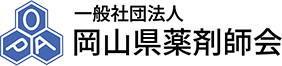厚生局による個別指導等において、外来服薬支援料2について次のような指摘事項があります。
- 治療上の必要性が認められない場合に算定している。
- 治療上の必要性が認められると判断していない。
- 当該薬剤を処方した保険医に次の事項の了解を得ていない場合に算定している。
□ 治療上の必要性
□ 服薬管理に係る支援の必要性 - 外来服薬支援料1を算定している。
- 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、[医師の了解を得た旨・一包化の理由]を薬剤服用歴等に記載していない。
- 調剤後について、患者の服用薬や服薬状況に関する情報等の把握、必要に応じた処方医への情報提供を行っていない。
などです。
これらの指摘は、外来服薬支援料2が「対人業務」として評価されるものであるという点を十分に理解されていないことが原因であると考えられます。
一包化は、令和4年度の調剤報酬改定以前は対物業務としての評価でした。薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進の観点から、令和4年度の調剤報酬改定においてそれまでの「一包化加算」は調剤技術料から薬学管理料に移管され、「外来服薬支援料2」として新たに評価されることとなりました。
算定要件は以下のとおりです。
「多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者」に対して、当該薬剤を処方した保険医に「当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性」の了解を得た上で、「2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い」かつ、「患者の服薬管理を支援した場合に」当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
すなわち、単なる一包化ではなく、薬剤師の専門的判断と医師との連携、患者への継続的支援が必要とされている点が重要です。
また、保医発0305第4号(令和6年3月5日)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において以下のような通知があります。(一部抜粋)
- 外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合について評価するものである。
- 外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算した点数を、投与日数が43日分以上の場合には、投与日数にかかわらず240点を算定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。
- 略
- 保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する
- 患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。
- 6~10略
外来服薬支援料2の算定においてはこれらをよく理解しておくことが必要であり、一包化にあたっては、内服用固形剤の種類や剤数の要件のみならず、「治療上の必要性が認められると判断する」ことが重要な要素となります。医師の指示による一包化においても治療上の必要性が認められなければ保険適用とはなりません。その判断をするのも薬剤師です。治療上の必要性については薬剤服用歴等への記載が必要ですが、その際「コンプライアンス不良」のような漠然とした記載ではなく、なぜコンプライアンス不良になっているか等、より具体的な記載が求められます。
また、令和6年度の調剤報酬改定において、外来服薬支援料2に施設連携加算が新設されました。これは、高齢者施設での薬剤師の支援業務も評価対象とするものであり、薬剤師が支援や指導の必要性を判断する点としては、従来と変わりません。
さらに、中央社会保険医療協議会 総会(第616回)(令和7年9月10日)におきまして、「現状を踏まえ、薬剤師の対人業務を拡充させる観点から、薬学管理料(調剤管理料、かかりつけ薬剤師指導料 等)における評価について、どのように考えるか。」が論点として挙げられています。
薬剤師の対人業務全体の視点と、その質の向上が今後ますます重要になります。現行の外来服薬支援料におきましても対人業務の視点でしっかりと算定要件を考えていく必要があります。