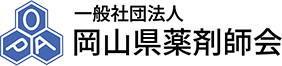地球上の生物は、およそ40億年前の原始生命の誕生以来、今日まで多種多様に分岐進化してきた。大きく植物系、動物類、微生物類(菌類)に分類される。植物は、無機物から有機物を合成することが出来るが、それは同時に物理的な太陽エネルギーを化学的エネルギーに転換することである。動物は、植物が作り出す有機物、化学的エネルギーを成長増殖し、更に生活行動に必要な物質・エネルギーに転換して生きている。結局植物の葉の中の葉緑素が行っている光合成が、全ての生命を支えている。
微生物、菌類はすべての生物の生産物、排出物、遺体などの有機物を分解して無機物に還元する。そのことによって、微生物・菌類は自分たちの身体の構成材料とエネルギーを獲得する。
今回は、木の知恵、竹の知恵、カイコの知恵、クモの知恵を考えてみる。
木の知恵
外からの支えを何も持たない木は、自分の根だけを頼りに、数百年、数千年も風雪に耐えて立っている。大地に根を張った植物はひたすら、その場所で耐えなければならない。これは大変なことである。細胞は、細胞の成長がとまると、細胞壁が少しずつ厚くなる。
内側から細胞の原料であるブドウ糖を何層にも塗るような活動をする。その結果、細胞壁の厚さは何倍にもなり、樹幹が数百年もの間、風雪にも耐えるようになる。この樹幹の中は生きていて、栄養分であるデンプン、糖、脂肪を含み、これらからフェノール、フラボノールなどを合成、抽出して、防腐、防虫、防菌剤として働く。つまり鳥や、昆虫や微生物を最終的に近づけない有害な物質に作り替えることを行う。
木には樹齢と耐用年数の二つの命がある。木材は上手に使えば、樹齢と同年の耐容が可能であるという。法隆寺のヒノキはこれから先相当持ちそうである。
竹の知恵
竹は縄文時代から、漆器、籠などの生活用具として利用されてきた。竹の構造の特徴に、棹に節がある。この節が驚異的な速さの成長のメカニズムに関わって、各節がそれぞれ独立に成長する。竹の繁殖能力2~3年でピークを迎え、5年後以降は殆ど成長しない。
竹の空洞の秘められた力は、しなやかさと強さがある。風に揺れても倒れない、しなやかさがある。その為、建材や楽器になる強さがある。
神秘的な存在として、昔から、物語や信仰の対象になった。生物学的ミステリーとして、竹は地下茎で広がり、群生をつくる。一つの群落は「巨大な一つの植物」ともいえる。つまり、竹林全体が一つの生命体のように呼吸している。まるで自然界の中にひそむ、神のメッセージみたいな植物である。
カイコの知恵
カイコは、人間とも長い歴史を持つ昆虫である。野生にはほとんど存在せず、人間が絹を得るために家畜化した家畜昆虫である。
幼虫は桑の葉しか食べない。これが最大の特徴。一生のうち4回脱皮して5歳幼虫になる。成長すると糸を吐き、繭をつくる。
繭は一本の長い糸(1500m以上!)で出来ている。この繭から取れるのが「絹糸」。古代から衣類や芸術品に利用されてきた。
絹糸の主成分は「フィブロイン」という蛋白質で、つややかで強い。成虫は白く、ずんぐりして、ほとんど飛べない。口が退化していてエサを食べない。数日で交尾、産卵して一生を終える。産卵数は数百個である。中国では5000年以上前から養蚕が始まり、日本でも古代から盛んに行われた。
シルクロードの名の通り、絹は世界を結ぶ重要な産業だった。現代ではナイロンなど化学繊維に押されているが、研究用や伝統工芸の為に飼育が続けられている。
クモの知恵
昆虫ではなく、クモ鋼(節足動物門)に属する。昆虫は6本足だが、クモは8本足。体は頭胸部と腹部の2つに分かれている。お尻からクモの糸を出す。クモの糸は同じ太さの鋼鉄よりも強い!
用途はいろいろで、巣作り(網を張る)、得物を捕らえる(粘着糸で絡めとる)、空を飛ぶ(バールーニング:子グモが糸に風を受けて空へ)。
昆虫などの小動物を捕まえて食べる。牙(毒腺を持つ)で獲物に消化液を注入し、体外消化して吸い取る。
生活の多様性として、網を張るクモ(ヂョロウグモなど)、網を作らず素早く動いて獲物を狩るクモ(ハエトリグモ)
人家にもよく出る(アシダカグモ)がいる。人間にとっては害虫を食べてくれる「益虫」的存在である。
クモは、糸で獲物を捕らえる、肉食のハンターであり、人間社会にとっては「害虫退治の名人」として貢献している。
クモと言えば、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」がすぐに思い出されることである。