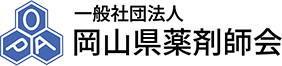2025年4月20日(日)、令和7年度第1回薬学講習会を開催しました。昭和医科大学薬学部の倉田なおみ先生に『摂食嚥下障害と錠剤(薬)嚥下障害』についてご講演いただきました。簡易懸濁法の第一人者である倉田先生の講義とあって、聴講者は386名と、大変多くの方にご参加いただきました。
「錠剤(薬)嚥下障害」とは、薬を飲むことに何らかの困難感があることで、いわゆる薬の副作用で起こる嚥下機能障害の「薬剤性嚥下障害」とは異なります。服薬は食べ物の嚥下よりも難易度が高いです。食べ物の嚥下は、よく噛んでペースト状になった均一の食塊を嚥下しますが、薬の嚥下は、固形物(薬)と液体(水)の物性の異なるものを同時に処理する必要があり、より高度な嚥下機能が必要なため、難易度が高くなります。食べ物の嚥下障害はなくても、錠剤(薬)が飲み込みにくい人がいる。この視点で患者さん向けのアセスメントツールPILL-5(日本語版)を用いた錠剤嚥下障害に関する調査を行ったところ、服薬のたびに飲みにくさをがまんしたり、それを誰にも相談せず、飲みやすくできるとも思っていない、という潜在的錠剤(薬)嚥下障害の患者さんが、6人に1人という結果となりました。
また、嚥下機能の低下の原因の一つに、口腔内乾燥が挙げられることから、特に高齢者に対しては口腔内乾燥を確認することで、服薬方法の改善が必要な患者さんを見つけることができる、といったポイントも話されました。
後半は、錠剤の製造過程を踏まえ、薬剤師ならではの視点で、粉砕不可の薬を潰さない重要性を多職種に伝える薬剤師の使命について、メッセージが込められていました。